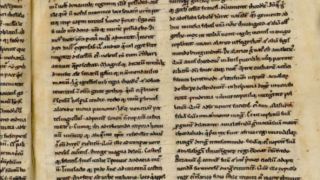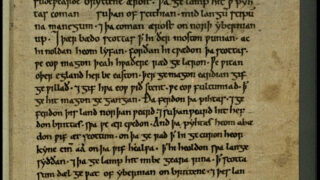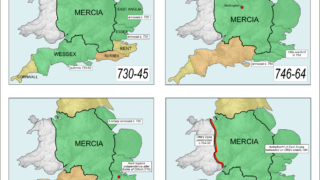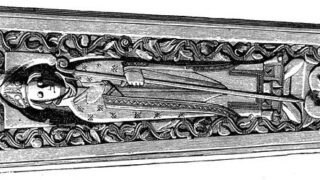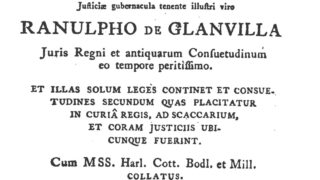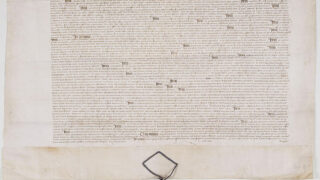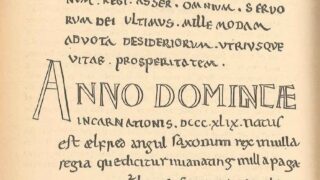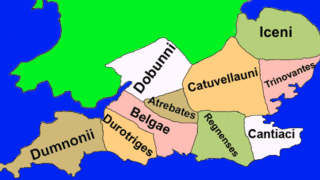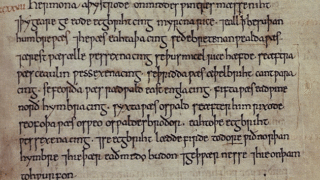「尊い……」ってなる、という記録が実際残されている。
記録を残しているのはゴベール・ティボーという準騎士で1429年三月二十二日、神学者のピエール・ド・ヴェルサイユの共としてジャンヌ・ダルクと面会したことがある人物である。彼はのちに兵士たちに率直に尋ねてみたのだそうだ。「お前らジャンヌ・ラ・ピュセルと一緒にいてムラムラしないの?」と。そしてそのやり取りを以下の通り書き残した。
「軍隊においては、彼女はいつも兵士たちと行動を共にしていた。ジャンヌと親しかった者の多くから直接聞いたことだが、彼女に対して彼らが肉欲を感じることは金輪際なかったという。それはどういうことかというと、彼らが彼女に欲情を抱くことはままあったにせよ、どうしてもそれ以上の挙に出ることはできなかったので、彼らは彼女を欲望の対象にすることは不可能だと信じこむようになっていた。仲間同士で、肉欲を満たし、快楽を刺激するような話をしあったり、言葉を口にしたりしているようなときでも、彼女の姿が目に見え、彼女の方に近づいていくと、もはやそのような内容は口にできなくなり、突如として性的興奮は失せはててしまうのであった。この点に関しては夜ジャンヌのかたわらで就寝したことが何度もある兵たちの何人かに尋ねてみたが、彼らの答えは今いったとおりで、彼女と面と向かっているときには決して欲情を抱くことはなかったとつけ加えていた。」(1ペルヌー、レジーヌ/クラン、マリ=ヴェロニック(1992)『ジャンヌ・ダルク』東京書籍、78頁)
おそらくこの記録をもとにしていると思われる創作として、山岸凉子のジャンヌ・ダルク伝記漫画「レベレーション(啓示)」でジャンヌのシノン行を共にした弓兵リシャールがジャンヌを襲おうとしたができなかったエピソードが描かれている。
ジャンヌの戦友二人の証言
同様のことを、やはりジャンヌとともに戦った準騎士ジャン・ド・メス(ジャン・ド・ヌイヨンポン)も語っている。
「旅の途中では、ベルトランと私は二人とも毎晩彼女と一緒に寝たのですが、乙女は胴着とズボンをつけたまま私の側で横になっていました。私は彼女に畏敬の気持ちを抱いていたので、彼女を誘惑するような気持ちは起きませんでした。誓って申しますが、私は彼女に対して欲望や肉体的衝動はもたなかったのです。」(2ペルヌー、レジーヌ(2002)『ジャンヌ・ダルク復権裁判』白水社、123-124頁)
ジャン・ド・メスはジャンヌの最初の理解者として知られる。ヴォークルール城主ロベール・ド・ボードリクールの配下の準騎士で、赤い服の少女が城下に訪れて城主に会わせろ、フランス王を救う、と騒いでいる様子を面白がって彼女をからかってみるも、その真摯な受け答えに感銘を受けて彼女――ジャンヌ・ラ・ピュセルを国王の下に連れていくことを約束する。
「信頼の徴として私の手を乙女の手の中に置いて、神にかけて国王の許に案内しようと乙女に約束しました。」(3ペルヌー(2002)122頁)
そのうえで、女性の服装では動き難かろうと自身の従者の服を貸し与えた。その後、ヴォークルールの住人たちが彼女の為に男の服を準備することになるが、彼が最初にジャンヌを男装させたのである。彼はその誓いを守ってヴォークルールからシノン城、そしてオルレアン包囲戦へとジャンヌを守って戦うことになる。
同じくジャン・ド・メスとともにジャンヌのシノン行を護衛したベルトラン・ド・プーランジの証言も一致している。
「彼女は毎晩、ジャン・ド・メスと私と一緒に寝ましたが、彼女は長い上着とズボンをつなぎあわせ、しっかり身につけていました、そのころ私は若かったのですが、彼女の体に触れようという欲求や衝動は覚えませんでした。私は彼女の中に感じられる善なるもののために、ジャンヌをものにしようという気は起らなかったのです。」(4ペルヌー(2002)130頁)
どちらも1456年に行われたジャンヌ・ダルク復権裁判での証言で、証言時ジャン・ド・メスは57歳、ベルトラン・ド・プーランジは63歳。ジャンヌとの旅から27年経っているので当時は30歳と36歳と男盛りの騎士だった。
大貴族アランソン公ジャン2世の証言
このようなジャンヌ尊い勢は彼らだけではない。ジャンヌ第一の戦友との誉れ高い貴族アランソン公ジャン2世もその一人である。彼も復権裁判で以下のような証言をしている。
「時には部隊の中では、私はジャンヌや他の兵士たちと『藁束の中で』寝ました。時にはジャンヌが夜の支度をするのを見たこともありますし、美しい乳房を目にしたこともあります。しかし肉体的欲望を覚えたことはありません。」(5ペルヌー(2002)192頁)
「ジャンヌは美乳」ここ試験に出ます。
アランソン公ジャン2世は美男公の異名で知られた貴公子でヴァロワ王家の傍流にあたる名門貴族である。シャルル7世から王太子ルイ(のちのルイ11世)の代父を任されるほど高い信頼を得ていた。シノン城でジャンヌと知り合い、オルレアン包囲戦には参加していないがその後のパテーの戦いまでのイングランド軍追撃作戦の総指揮を執り、シャルル7世のランス戴冠の立役者となった。戴冠式では王冠を支え持つ諸侯筆頭の役割を与えられている。
しかし、ジャンヌと非常に親しく彼女に心酔して対英主戦派の領袖となっていったことが彼の運命を変えた。ジャンヌ死後、集権化を進める王と諸侯の対立、王太子ルイとシャルル7世との確執などが相まって、アランソン公は王と衝突するようになり、1440年、プラグリーの乱ではブルボン公とともに首謀者として王太子ルイを擁立して反旗を翻した。反乱鎮圧後許されても王との対立は解消されず、この復権裁判での証言の直後、大逆罪で逮捕され、1476年に67歳で死ぬまで獄中の人となる。第一の忠臣から最大の反逆者へと堕ちた彼の人生からわかる通り、ジャンヌに心酔しすぎて身を滅ぼすという後世の創作ではジル・ド・レに与えられることの多い役回りを実際にたどった人物である。
そんな彼だけに、このジャンヌ美乳エピソードに限らず様々なジャンヌとの美しい思い出を語っている。彼にとってジャンヌとともに駆け抜けたあの頃というのは栄光の時代そのものだったのだと思わされる。
いや、アランソン公はジャンヌガチ勢すぎない?という人のためにもう少し冷静な人物の証言も紹介しておこう。ジャンヌの副官ジャン・ドーロンもジャンヌに欲情したのか問題についてこのような証言をしている。
ジャンヌの副官ジャン・ドーロンの証言
「彼女は美しくて成熟した若い娘であり、またあるときは彼女が武装するのを手伝ったりする折に、私は彼女の乳房や、時には傷の手当てをしてやるために何もまとわない脚を目にすることもありましたし、度々彼女に近づくこともありました――一方私のほうも頑健で、若くて、力に満ちていたのですが――しかし乙女の体を眺めたり、乙女に触れたりする機会があったにもかかわらず、私には彼女に対する肉体的欲望は絶対に起きませんでした。またこれは彼女の部下や近習たちのだれもが同様で、このことを彼らが語るのを何度も聞いています・・・・・・。」(6ペルヌー(2002)208頁)
後世、ジャンヌ美人じゃなかった説も囁かれたりして、実際、ジャンヌの見た目については記録が残っていないためわかっていないが、当時のもっとも身近だった人物であるジャン・ドーロンは「美しくて成熟した」とはっきり書いているという例として挙げておこう。
ドーロンは国王からの信頼も厚く、ジャンヌの副官として部隊の維持にその手腕を発揮、コンピエーニュではジャンヌとともに捕虜となり、そのあと解放されてからも百年戦争で活躍、復権裁判当時は南フランスの要衝ボーケールを任され、国王顧問会議の一員にも名を連ねるシャルル7世の重臣となっている。
フランス側の当時のジャンヌ熱は実際強くてシャルル7世の側近の中には「マジ天使」などと言う者も本当にいた。とはいえ、ジャンヌは天使の声を聴いたのであってジャンヌ自身が天使なのではない。尊い・・・でとどめておいてもらわないと、実際、天使であってはジャンヌの異端性を否定する上で非常に困るので、そのあたりのマジ天使!な熱狂的な人たちは、復権裁判時は丁重に無視される。
中世の女性観~魂と身体の純潔性
一方、ジャンヌが囚われている間に関する証言としてこんなものがある。証言者はエーモン・ド・マッシーというブルゴーニュ騎士である。当時ブルゴーニュはイングランドの同盟国でフランス王と対立していた。ジャンヌをとらえたのもブルゴーニュ公国のリニー伯軍であった。エーモン・ド・マッシーは主君であり、ジャンヌをとらえてイングランドに引き渡すことになるリニー伯ジャン・ド・リュクサンブールの共として、リニー伯が所有するボールヴォワール城に囚われているジャンヌと面会し、実に最低な行為に及んだ。
「私がはじめてジャンヌにあったのは、彼女がリニー伯殿の監督権のもとでボールヴォワールの城に監禁されていたときのことです。私は牢獄で数回彼女に会っており、何度も話をしています。ふざけながらですが、私は何度か彼女の胸に手を置いて乳房に触れようとしたことがありますが、ジャンヌは許しませんでしたし、力一杯私をはねつけました。ジャンヌは言葉使いでも、振る舞いでも間違いなく真面目な態度を崩しませんでした。」(7ペルヌー(2002)230頁)
中世の女性観というのは非常に残酷である。純潔性をことさら重視して身体の純潔性と魂の純潔性とを相互に補完させることを求める。一方で性的な暴力の危険は実に多く存在する。
「中世の司法は、ごく若い娘と聖別された処女の強姦を非常に厳しく罰する。しかし、抵抗しなかったり、叫んだり助けを呼ばなかったりした被害者は、合意しているとみなされる。もっともこの身体の純潔を防御するという点では、神は奇蹟によって処女たちを救う。」(8ボーヌ、コレット(2014)『幻想のジャンヌ・ダルク―中世の想像力と社会』昭和堂、152頁)
ゆえに、前述のジャンヌの戦友たちの証言は魂と身体の純潔性とが結びついた存在としてジャンヌを見ていた結果として理解できよう――ジャンヌに魂の純潔性を見ていたがゆえにジャンヌの身体に対する性的な欲求を、おそらく意図せず至極当然のこととして自ら抑えていた――そういう中世的心性が見え隠れする。このように一次史料をただ受け入れるのではなく当時の心性を考慮して読み解くというのは史料にあたる上での面白さの一つである。もちろん、復権裁判での供述の総体が導こうとしている方向が、その彼女の純潔性ゆえの異端判決の棄却であるという点も考慮しなければならない。
これに対して、ジャンヌの処刑裁判においては、まさにその魂と身体の純潔性をこそ穢すことが目指された。しかし、その彼女の身体の純潔を汚すことはできなかったと考えられている。これに重要な役割を担ったのが、ベッドフォード公妃アンヌ・ド・ブルゴーニュである。
ベッドフォード公ジョンは先王ヘンリ5世の弟で幼王ヘンリ6世を摂政として補佐し、対仏戦争の総指揮を執るイングランドの最高権力者である。イングランドの快進撃は彼の辣腕が支えていたし、ジャンヌの処刑も彼の意志によるところが大きい。その妻アンヌはその名の通りブルゴーニュ公フィリップ3世の妹にあたる。当時、イングランドはフランス王から離反したブルゴーニュ公国と同盟することによって百年戦争を有利に進めることができていた。しかし、オルレアン包囲戦前から両者の同盟関係は悪化しており、特にイングランドはブルゴーニュとの関係改善をもくろんでいる最中だった。その両国の同盟関係をつなぐ最重要人物が彼女だった。
ベッドフォード公妃アンヌは興味深い人物である。貧民救済に積極的で自ら庶民の間に入って救貧活動を行ったりする。結局その活動が元で病気になり1432年に亡くなるのだが、彼女の死によって、かすがいを失ったアングロ・ブルギニョン同盟は崩壊、1435年のベッドフォード公の死を契機として同年アラス和約でフランスとブルゴーニュ公が和解し、孤立したイングランドは最終的に大陸領土のほぼすべてを失って百年戦争の終了へといたる。
ジャンヌ・ダルク処刑裁判において、アンヌはジャンヌの純潔検査を監督、彼女の態度に感銘を受け、その上で「彼女に対して手荒な扱いをしないよう獄卒たちに命じている」(9ペルヌー、レジーヌ/クラン、マリ=ヴェロニック(1992)『ジャンヌ・ダルク』東京書籍、198頁)。この命令の強さは当時のイングランドにおける彼女の存在の重要性からうかがいしれよう。たとえ敵方であっても権力にある者として弱い立場にあるジャンヌを守ろうとしたベッドフォード公妃アンヌという女性がいたという点は、特筆されてよい。
実際、処刑裁判では、日常的な虐待はもちろんあり毒を盛られたのではと疑われる事態もあるしジャンヌ自身常に性的な暴力を受ける危険を感じていたが、少なくとも彼女の純潔性が守られる前提で審理が進むことになった。さらに裁判官たちも一枚岩ではなく少なからずジャンヌに同情的な者たちも多く、ジャンヌ自身が毅然とした態度で審理に臨んだことで、ピエール・コーションをはじめとする親英派の裁判官たちはあれこれと小細工を弄して、「誓いを破って再び男装した」=「戻り異端」という無理あるロジックでの処刑をせざるをえなくなる。
ジャンヌに対して同時代の人々は欲情したのか?という軽めな問いの結果、浮かび上がってくる中世的心性と女性に対する宗教的性規範観、というアプローチはなかなか興味深いと思うので、誰か研究者の掘り下げに期待したいと思い、本邦ではあまり知られていないだろうジャンヌ関連人物のエピソードも交えて簡単に紹介してみた。
参考書籍
- ペルヌー、レジーヌ/クラン、マリ=ヴェロニック(1992)『ジャンヌ・ダルク』東京書籍
- ペルヌー、レジーヌ(2002)『ジャンヌ・ダルク復権裁判』白水社
- ボーヌ、コレット(2014)『幻想のジャンヌ・ダルク―中世の想像力と社会』昭和堂
- キュンク、ハンス(2016)『キリスト教は女性をどう見てきたか 原始教会から現代まで』教文館